稼働率100%でも黒字化が困難な現状
急性期病院、特に高度急性期病院において、病床稼働率が100%近くなければ黒字経営が困難になっている深刻な状況が明らかになっています。この問題の背景には複数の要因が絡み合っており、医療提供体制の持続可能性に大きな課題を投げかけています。
急性期病院の経営実態
高度急性期・急性期病院では、「黒字を出すためには稼働率100%を維持しなければならない」という異常事態が生じています。これは、ベッドコントロールにわずかな齟齬があるだけで次の予定患者を受け入れられなくなったり、緊急入院の受け入れが困難になったりするなど、地域医療の崩壊にもつながりかねない問題です。
実際のデータを見ると、黒字病院と赤字病院の病床稼働率には明確な差があります。平成24・25年度の比較では、黒字病院の病床稼働率が98.7%であるのに対し、赤字病院は91.7%となっています。つまり、黒字経営のためには100%近い病床稼働率が必要とされているのです。
赤字経営の実態と原因
1. 人件費の問題
収益に対して人件費の割合が高いほど、赤字になりやすい傾向があります。平成20年度の人件費比率は赤字病院が54.7%、黒字病院が51.8%と、赤字病院が2.9%高い数値となっています。国公立病院では特に看護師やメディカルスタッフの給与費額が高く、これが赤字の一因となっています。
2. 物価高騰と診療報酬の乖離
物価高騰・人件費高騰に対して診療報酬が十分に対応していないことも大きな要因です。2年間固定される診療報酬では、急激な物価・人件費高騰に対応できず、また医療機関の負担する控除対象外消費税も想定を上回る負担となっています。
3. 医療機能と収益性の関係
興味深いことに、医療機能が高度であるほど医業収支の赤字幅は大きくなる傾向があります。高度な医療機能を担うためには収益に対して多額の設備投資が必要となり、効率的に収益を上げられるわけではありません。
病院規模別の財務状況
2022年度の医療経済実態調査によると、100床当たりの損益差額のマイナスが最も大きいのは500床以上の病院(1.8億円)であり、500床以上の病院では年間9億円の赤字になるという深刻な状況にあります。大病院はスケールメリットがあり、100床当たりの手術件数などの診療実績も豊富であるにもかかわらず、黒字基調に推移していないのが現状です。
損益分岐点としての病床稼働率
一般的に、病院の損益分岐点となる病床稼働率は病院の種類によって異なります。一般病院では88.2%、ケアミックス病院では84.9%、療養型病院では91.6%、精神科病院では90.0%が損益分岐点とされています。しかし、急性期病院、特に高度急性期病院では、この数字が100%近くまで上昇しているのが現状です。
今後の展望と対策
この状況を改善するためには、診療報酬の「期中改定」などの対応を求めていくとともに、病院側も診療報酬の算定漏れがないか確認する、DPCの機能評価係数II向上に向けた取り組みを進める、地域連携をこれまで以上に進めるなどの経営安定策を検討していく必要があります。
また、全国自治体病院協議会では2025年度から各自治体病院の経営・診療データを集積してデータベース化し、ベンチマーク分析などによる経営支援やデータに基づく政策提言につなげる「データクラウド事業」を立ち上げる予定です。
高度急性期医療の提供体制を維持するためには、適切な財政支援と医療機能の見直しのバランスが重要となります。地域のニーズや周辺の環境に合わせて、柔軟に医療機能転換の検討を行う必要性が今、問われているのではないでしょうか。

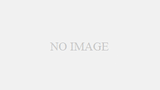
コメント